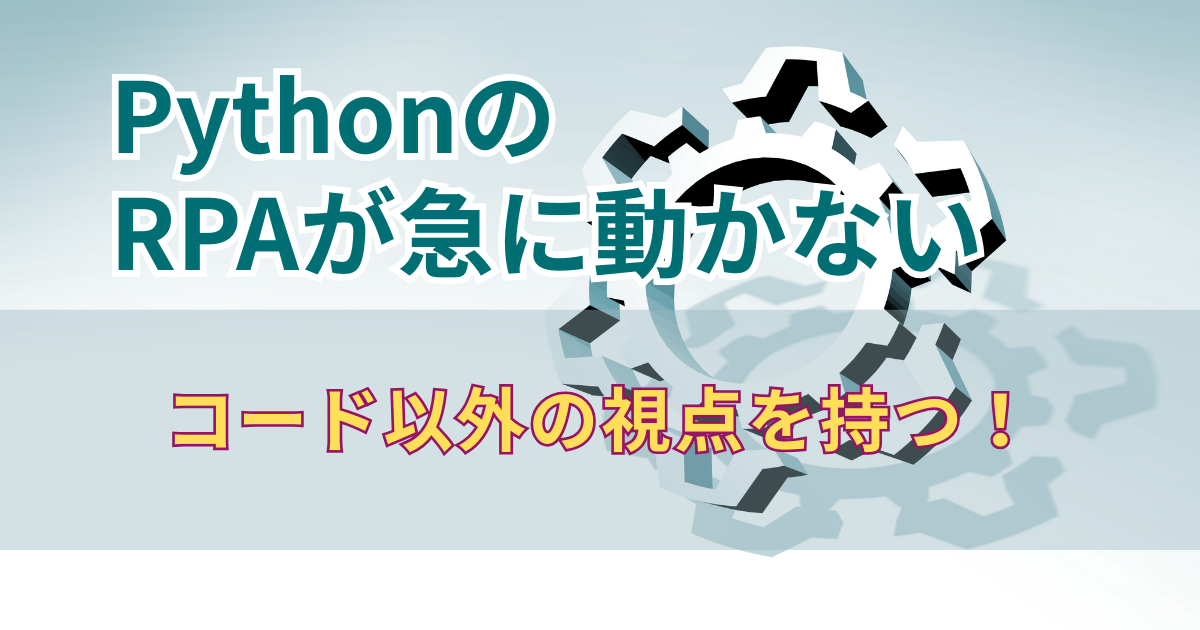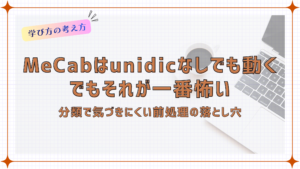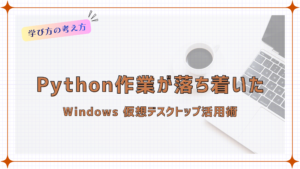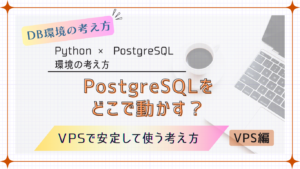PythonでRPAを組んで、自分の作業を自動化するのはとても楽しい時間でした。
マウスを自動でクリックしてくれたり、テキストを入力してくれたり。
毎日のルーチンがぐっと楽になり、「もう手放せない」と思うほど便利な存在です。
ところがある日、そのRPAが急に不調に陥りました。
いつもなら1秒で終わる処理が、3秒、5秒とかかる。クリックはズレ、入力も途切れがち。
昨日までは普通に動いていたのに、どうして今日はダメなのか。
この不思議な現象がきっかけで、私は数日にわたる「原因探しの旅」に出ることになったのです。
導入:突然訪れた「動かない」日
PythonでRPAを組んで、自分の作業を少しずつ自動化していくのは本当に楽しいものです。
私も毎日のように、pyautoguiを使ってちょっとした自動操作を行っていました。
ボタンをクリックしてくれる、テキストを入力してくれる、Excelを自動で開いて処理してくれる。
自分がやらなくてもパソコンが代わりに動いてくれるのは、まさに「小さな秘書」を持ったような感覚です。
ところが、ある日その「秘書」が急に働かなくなったのです。
- クリックがワンテンポ遅れる
- 入力が途切れる
- 画面遷移が間に合わず処理が止まる
昨日まではサクサク動いていたはずなのに、今日はどこかぎこちない。
まるで同じ人が別人になったように、RPAが頼りなくなってしまったのです。
「一体なぜ?昨日と何が違うの?」
私はそこから数日にわたる“原因探しの旅”に出ることになりました。
不調が始まった日と焦り
その日は特別なことをしたわけではありませんでした。
いつものようにノートPCを開き、仮想環境を有効化して、いつものスクリプトを実行。
ところが、待っていたのは「妙に遅い反応」でした。
普段なら1秒で終わる操作が、3秒、5秒とかかる。
画面のボタンを押すタイミングがずれて、うまく処理が進まない。
最初は「ちょっと遅いだけかな」と軽く考えました。
ですが、同じスクリプトを何度走らせても、やはり挙動がおかしい。
しかもその日は仕事の準備でどうしてもRPAを動かしたかった。
「今日中に解決しないと困る」という焦りが、頭の中を支配し始めました。
数日の試行錯誤:コードを疑い続けた日々
1日目:コードのミスを探す
最初に疑ったのはやはりコードです。
「自分が何か間違えたのでは?」と思い、何度もソースコードを読み返しました。
- コメントアウトして部分的に動かしてみる
time.sleep()の秒数を増やして挙動を確認- 条件分岐のロジックを見直す
しかし、どれも効果なし。
プログラムの流れ自体は正しいのに、動作だけが遅いのです。
「おかしいな…。昨日まで普通に動いていたのに」
2日目:環境のせいだと思い始める
翌日は「もしかして環境の問題では?」と思い、次のことを試しました。
- 仮想環境を新しく作り直す
pyautoguiや依存ライブラリを再インストール- 使っているPythonのバージョンを切り替える
しかし、改善せず。
「やっぱり自分のスキル不足かもしれない」
そんな思いが頭をよぎり、少し落ち込みました。
3日目:疑心暗鬼になる
さらに別のPCでも試してみましたが、やはり不調。
今度は「ライブラリの不具合?」「Windowsのアップデートの影響?」と、疑いは広がるばかり。
ネットで検索してもピタリと当てはまる情報は見つからず、時間だけが過ぎていきました。
「RPAってやっぱり安定しないのかな」
「自分の実装力が足りないんじゃないか」
そんな思いに駆られて、Python学習そのものが嫌になりかけたほどです。
ふとした気づきの瞬間
数日悩み続けて、もう諦めかけていたときのこと。
ふと、画面右下のバッテリーアイコンが目に入りました。
「あれ?今日はACアダプタを抜いて使っているな」
何気なく電源設定を開いてみると、「省電力モード」に切り替わっていることに気づきました。
その瞬間、直感的に思いました。
「もしかしてこれが原因なのでは?」
意外な真相
実際に調べてみると、WindowsやMacのノートPCは、バッテリー駆動時に自動的にCPUやGPUの性能を制限することがわかりました。
クロック数を下げることで、消費電力を抑えてバッテリーを長持ちさせる仕組みです。
日常のWeb閲覧や文書作成なら問題はありません。
ですが、RPAのように「タイミングに敏感な処理」では、この性能低下が大きく影響してしまうのです。
つまり、不調の原因は——
コードでもライブラリでもなく、PCの電源モードによる処理速度低下 でした。
解決と安堵
半信半疑でACアダプタを接続し、電源モードを「高パフォーマンス」に切り替えてみました。
するとどうでしょう。
さっきまで遅延だらけだったRPAが、見違えるようにスムーズに動き始めたのです。
クリックはぴたりと合い、入力も途切れず、画面遷移も完璧に追随。
昨日までの姿がそのまま戻ってきました。
数日にわたる悩みが、一瞬で解決。
思わず「なんだ、こんなことだったのか」と笑ってしまいました。
技術的な背景
ここで少し補足しておきます。
- バッテリー駆動時
CPU/GPUのクロック数を抑制(例:3GHz → 1.2GHz)
タスク処理速度が落ちる - 省電力モード
パフォーマンスよりもバッテリー寿命を優先
グラフィックやCPU性能が制限される - 高パフォーマンスモード
消費電力は増えるが、性能を最大限発揮
RPAは「処理速度の安定性」が非常に大切です。
一秒の遅れが積み重なると、クリックの座標がずれたり、入力が追いつかなかったりするからです。
つまり、RPAをノートPCで安定的に動かすには——
必ずACアダプタを接続して、高パフォーマンスモードで実行する ことが重要になります。
学びと教訓
今回の経験から得た最大の教訓は、これに尽きます。
「動かないときは、コード以外の要因も疑う」
プログラミング学習を始めたばかりだと、「エラーや不調=自分のコードが悪い」と思い込んでしまいがちです。
でも、実際には環境の設定やPCの状態が原因になることも少なくありません。
私の場合、数日も悩んでしまいました。
ですがそのおかげで「環境を理解することもまたプログラミングの一部」だと強く実感できました。
まとめ:コード以外の視点を持つ
PythonのオートGUIやRPAが「急に遅くなった」「動きが不安定になった」とき、
- ACアダプタを接続しているか
- 電源モードが省電力になっていないか
- 高パフォーマンスで動作しているか
これらを確認するだけで、一瞬で解決することがあります。
数日間の悩みは無駄ではありませんでした。
むしろ「コード以外の視点を持つ」という大きな学びを与えてくれたのです。
同じように悩んでいる方の助けになれば嬉しいです。
そして、エラーや不具合に出会ったときも「学びのきっかけ」として前向きに向き合えるようになれば、Python学習はもっと楽しく続けられるはずです。